 コラム「組織の成長加速法」-第177回 出来る奴がリスクになる、組織の病いに打ち勝つ!
コラム「組織の成長加速法」-第177回 出来る奴がリスクになる、組織の病いに打ち勝つ!
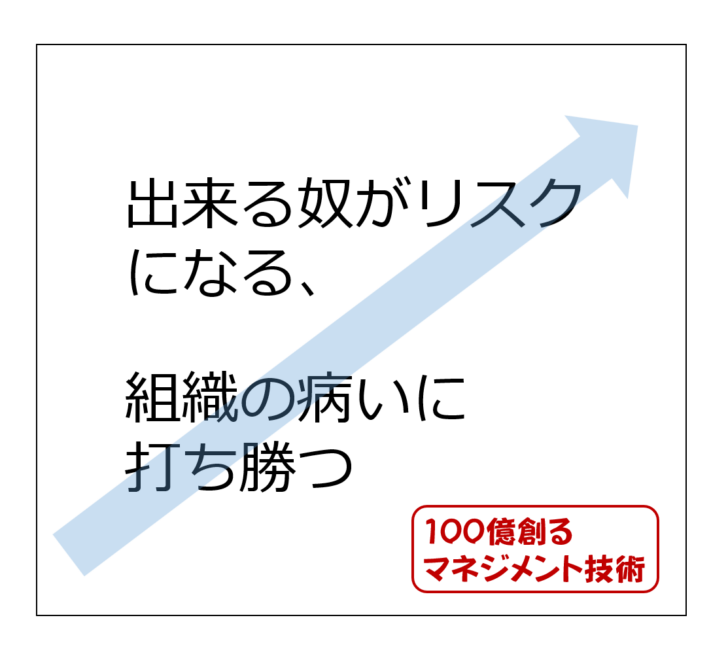
社会の構造変化に合わせて、その会社は急速に業績を拡大していました。ところが、その事業の核がたった一人の社員に委ねられていたのです。
ある日、その事業の担当取締役であるMさんが「木村先生、Yが辞めたいって言ってきまして。」とオロオロしながら話し始めました。Yさんというのが、その事業の核を握る30代の男性でした。
M取締役は、そのYさんのことをとても買っていて、「次の期には部長にしたい、部長になれば、社内で最年少部長です。」とまで言っていたのです。「Yにだけにしかできない。」「Yは、そのことに気がつく。」「Yがやると、精度が違う。」「Yみたいなとても社員が増えるといい。」と、Yさんの話になる度に、M取締役からは、Yさんを大絶賛していました。
初回の面談時に、M取締役から組織構成、事業内容の共有を受けていた時に、Yさんの役割も聞きました。
私は、M取締役に「Yさんお一人でやっているのですか?」と確認しました。M取締役は、「これは、Yにしかできないのですよ。」と涼しい顔でした。
私は、M取締役に図を書きながら、如何にYさん一人でやることに、リスクがあるかを説明していきました。そして、対処法として、2つのステップでシステム化することを提案したのです。
ところが、M取締役は意に介しませんでした。「木村先生、Yなら大丈夫です。彼女ほど信頼できる人にはあったことがありません。責任感があるんです。ある時なんか、38度もあるのに、午後から会社に出てきて、2日分の仕事、3時間でやってのけました。」と。
業種業態を超えて、Yさんのような役割をする社員が会社にいます。社内では、なかなかこのできる社員のリスクに気づくことがないのです。
伸びる会社ほど、このリスクを抱えるわけですが、昨日と今日で、売上げが2倍になるわけではないので、このリスクが顕在化してこないのです。しかし、これは当に、言葉通り、病気のように、徐々に確実に組織の未来を蝕んでいくのです。
この点は、社長は認識していて、M取締役にも対処をするように促しているとのことでしたが、2年たっても変わっていなかったのです。
そして、冒頭のやりとりです。
私はM取締役に、今こそ対処の時として、2ステップで対処することを実行することを提案しました。Yさんの前任者は沢山いたのですが、全員退職していました。Yさんの業務内容を一番理解している人は、M取締役でした。
M取締役は、この事業が始まって間もなく、Yさんの業務を5年ほど担当していたのです。M取締役がこの業務から離れる時、売上は現在の半分以下の15億円程度でした。当時40億を超えていました。
M取締役も、「(自分では)絶対にYと同じことはできない。」と念仏のように言っていましたが、風雲急を告げているため、M取締役にはプロジェクトリーダーになってもらいました。
まず、社内で適任者となり得る人を3人集めることにしました。2ステップでシステム化に向かって動き出しました。
1.3ヶ月でYさんを作業から離れてもらい、監督業務に徹してもらうこと。
2.同時並行で、システムの設計に取り組み1年後からシステムの導入に踏み切ること。
当時は、AIがなくて苦労しましたが、今なら、AI使えば、半年でシステムは組めたかもしれません。
その後、会社の業績は、更に倍となり、80億円を優に超えています。上場に向かってひた走っています。
M取締役は後日、教えてくれました。“Yさん一人に委ねてはまずい、今すぐ変えなければならない。”と覚悟を決めたのは、私からの問いかけだったそうです。
「今、これを変えなければ、上場するにあたって、最大の障害をMさん自身が創ることになる。それでもいいのですか?」と問われた時に、我に返ったとのことでした。
M取締役には夢があったのです。M取締役は、8年前のある日、この会社にアルバイトとして入社して、半年後に社員となりました。
会社の事業の急拡大に合わせて、多くの仲間との出会いと別れがあったそうです。大変な時期を乗り越えて、一緒に頑張ってきた仲間が誇れる会社を作りたい。というのがM取締役の夢でした。
M取締役の覚悟が決まって、“出来る奴がリスクになる、組織の病い”に打ち勝つことができました。
かつて、経営の神様と称されたジャック・ウェルチが「経営とは、中長期の目標と短期的な目標の相反することを実現することだ。」という旨の発言をしています。裏を返せば、多くの経営者が知らず知らず、どちらか一方に傾きがちということでもあります。
もし、あの時に、中長期の目標を見ないまま、小手先の対応をしたならば、今の時点で、この業績はありません。大きな周り道をすることになっていたはずです。経営の中枢にいる者は、長期も短期もどちらも見ることを常に忘れてはならない。
当たり前のことですが、常に確認したい視点です。